幸福のための人間のレベル論ー「気づいた」人から幸せになれる! 著者:藤本シゲユキ さくら舎
こんな人に読んでほしい
・生きづらい、自分は不幸だと思っている人
・幸せってなんだろう、私って幸せになれるのかな?と思っている人
・対人関係に悩んでいる人
・人と接するのが苦手な人
本を読んだ感想
人間のレベルと言われると、自分がどのレベルにいるのかとても気になります。
人間のレベル論は初見でしたが、図がカラフルでわかりやすく、面白かったです。
占いの本のようで、「なるほど〜」と思うこともあるし、グサッと刺さるところもありました。
自分はどのフィールドにいるのか、他者はどのフィールドにいるのかを考えながら読み進めました。
今まで、人間をレベルで考えたことはないですが、私もこの人とは話しても無駄だな、話が合わないなと思うことありました。人による考え方や、行動の違いであるということがわかって、スッキリしました。
大人になって、社会に出て、「親の言うことって正しくないかも」と思っていたけれど、でも、じゃあなにが正しいんだろうと漠然と思っていたことも、この本を読むとスッキリします。
自分を知るきっかけにもなる本だし、これから幸せになるための本でもあるし、人として成長するための本でもあります。
人間のレベル論が全てというわけではなく、考え方の一つとして、生きやすく幸せになる道を選んでいければいいなと思います。
人間のレベル論とは
人間の幸福レベルを、9段階のフィールドに分けたものが、人間のレベル論です。
上の階のフィールドに行けば行くほど、幸福を感じる能力が高くなる仕組みになっています。
[最下層] 人でなしステージ
けだものフィールド
きつねフィールド
[第一階層] 気づいていないステージ
うさぎフィールド
チワワフィールド
ハリネズミフィールド
[第二階層] 気づいているステージ
ねこフィールド
ライオンフィールド
[第三階層]悟りステージ
ペガサスフィールド
お釈迦様フィールド
ステージが上になればなるほど、幸福度が高い生き方ができるようになり、人や社会に愛を持って貢献できるようになるというのが、人間のレベル論です。
ステージやフィールドが上の人間が、人として優れているというわけではありません。
各層の割合
最下層〜第一階層 全人口のおよそ8割
第二階層〜第三階層 全人口およそ2割
お釈迦様フィールドは全人口1%未満
そして、この人間レベルは、フィールドアップ、ステージアップもありますが、フィールドダウン、ステージダウンもあります。
この人間レベルは、仕事の場でのフィールドと、恋愛の場でのフィールドで、レベルが変わることもあります。
人間には光の性格もあれば闇の性格もある
どんな人にでも、光の性格もありますし、闇の性格もあります。
光の性格が出れば出るほど、人は、愛をベースにした、陽極に沿った生き方ができるようになり、『人生や人間の心理』を得ることによって、人間レベルがステージアップしていきます。
逆に闇の性格が出れば出るほど、人は、恐怖や憎しみをベースにした、陰極に沿った生き方をするようになります。(多くの人が目を背けて見ようとせず、認めたくない自分の嫌な部分がこの闇の性格になります。)
どれだけ優しい人にも、闇の性格はありますし、犯罪者にも光の性格があります。
どうせなら、光の性格を全面に出していき、陽極の人生を歩んで気づきを得ていく方が、人生はものすごく楽しいし、人にも社会にも優しくできます。
各フィールドの物の捉え方
[最下層] 人でなしステージ :自分さえ良ければそれでいいという考えがベースにある
・けだものフィールド:「自分にとって利用価値があるだろうか」
・きつねフィールド:「誰か自分のこと助けてくれないかな」
[第一階層] 気づいていないステージ :自己防衛本能が働き、結果がわかりやすいものでないと行動できない
・うさぎフィールド:「何か不幸なことが起きそう・・・」
・チワワフィールド:「嫌われたんじゃないか・・・」
・ハリネズミフィールド:「何でそんなことも出来ないの?」
[第二階層] 気づいているステージ :目の前に起こっている現実は全て過去の自分が選択した結果
・ねこフィールド:「もっと楽しいことした」
・ライオンフィールド:「ここからなにを学べるんだろうか?」
[第三階層]悟りステージ :天命のもと人や社会に与えるという生き方
・ペガサスフィールド:「どうすればもっと与えられるだろうか?」
・お釈迦様フィールド:「一は全、全は一」
気づいているステージの人は何に気づいているのか?
まず、気づいていないステージの人と、気づいているステージの人の特徴を比べてみてみましょう。
気づいていないステージの人の特徴
- 自分の主観でしか物事を見られない
- 現実から目を背けている
- 自分のことがわかっていない
- 無い物ねだりをしている
- 全ては自己責任だと腑に落ちていない
- 感情論が多い
- 人と状況をコントロールするために躍起になる
- 自己開示ができない、開示しても自分の悪い部分は取り繕う
- 相手に何かをするときは自分のことを認めてほしいという承認欲しさからくる見返りありき
- 自分は幸せであると言い切れない
気づいている人の特徴
- 客観的視点であらゆる角度から物事を見ている
- 現実をしっかり見据えている
- 自分のことをわかっている
- 自分にないもの、できないことを理解して欲しがっていない
- 全ては自己責任だとわかっている
- 合理的、哲学的な思考である
- 人と状況はコントロールできないので、なるようにしかならないと思っている
- 自分の悪い部分を理解した上で自己開示ができる
- ギブアンドギブの精神で先に与える
- 自分は幸せだと言い切れる
両者の違いを見ると、真逆の性質であることがわかります。
気づいているステージの人は何に気づいているのか?
- 目の前に起こっている現実は、全て過去の自分が選択した結果である
- 人がどう思うかじゃなくて、自分がどう思うか
- 自分におこる悪い出来事や逆境は試練であり、乗り越えるべきもの
- やりたいことはやるしやりたくないことはやらない
- なるようにしかならない
ステージアップをするためには
- 全ては自己責任であるとわかる
- 自分を知る
- 自分にないものと悪い部分を自覚する
- 客観的思考を身につける
- 生きづらさの原因を作っている固定観念を解除する
- 自己肯定感を高める
- 世間体や人の評価に縛られずやりたいことをやる
- ゴールに必要がないやりたくないことはやらない
全ては自己責任であるとわかる
全ての過去と経験には意味があります。
今の自分が不幸であれ、幸福であれ、どれだけ無駄だと思った過去であっても、どれだけ経験したくないと思った過去であっても、その過去が1つでも欠けていたら、今の自分は存在しません。
色々な経験を通じて、『気づき』を得たことによって、今の自分があります。
起こった出来事に対して自分がどう感じるかは、「自分がどう受け止めて、どう解釈したか」だけです。
人のせいにしてずっと生きてきた人は、それが、目の前に起こっている現実は「全て過去の自分が選択した結果」であり、悪い出来事が起こるたびに、責任の所在を自分以外のものに求め続けた結果なのです。
自分を知る
自分の内面や特性に興味を持ち、自分がどういう人間であるかを知ることが「自分を知る」ということです。
自分を深掘りしていくと、自分にできることと、できないことを、区別できるようになり、自分の適材適所がわかるようになります。
自分のことを具体的にどうやって知っていくかというと、ただひたすら、自分に問いかけます。そして答えが出たら、それに対して「なぜ?」とさらに問いかけます。
例えば、「自分が嬉しいと感じるときはどんなときか?」の答えが出たら、「なぜ自分はそれを嬉しく思うのか?」と深掘りしていきます。
自分を知るということは、1週間や、1ヶ月でできる作業ではなく、一生をかけてする作業です。
人や経験を通じて自分を知る手がかりを得ることができるので、その手がかりをたくさん手に入れて、問いかけていくことで、どんどん自分のことを知っていけるのです。
自分にないものと悪い部分を自覚する
ないものが何かわかっていない人が、あるものに目を向けても、日常感じる「欠乏感」がどこからくるものかわかっていないので、結局「ないものねだり」をしてしまいます。
ないものがなんなのか、何をそんなに求めているのかを自覚することが、現実を知る第一歩になります。
どれだけ認めたくないことでも、泣き叫ぼうが、喚こうが、現実は何も変わりません。
ないものは、ないのです。
ないものを自覚するということは、今の自分の状態を受け入れるということで、これは運命を受け入れるということになります。
現実を知るということは、自分の悪い部分を自覚するということでもあります。
自分の悪い部分というのは、自分が思っている以上に根深いもので、自覚していない人は、日常から、「無自覚に」自分の悪い部分を出してしまっているので、隠そうとしていても滲み出てしまっているということです。
- 相手への配慮が足りない
- 手のひら返し
- 上から目線
- 感謝ができない
- 自意識過剰
- 都合が悪くなったら逃げる など…
悪い部分をしっかりと自覚した上で、その悪い部分と改善しようと心がけることが必要になります。
なりたい自分になる
なりたい自分を思い描いたら、「理想の自分になる!」と『決める』ことが第一歩で、あとはひたすら、その自分になるために、ふさわしい行動を、積み重ねていくだけです。
- 自分にないものを自覚して受け入れ、その上でどうするべきかと考える
- 自分の悪い部分を自覚して受け入れ、悪い部分と真逆の生き方を心がける
- 理想の自分になると決める
- 理想の自分にふさわしい行動を習慣になるまで積み重ねる
思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。
マザーテレサ
全ては、自分の思考によって、現在の自分が作られています。
客観的思考を身につける
客観的思考を身につけるのは、これから説明する「固定観念の解除」をするためです。
物事の受け取り方
- 妥協
- 拒絶
- 不安
- 悲嘆
- 共感
- 客観的思考
1〜5は感情的な受け取り方で、6だけが合理的な受け取り方です。
客観的思考は、つい感情で考えてしまう物事に対して、そのまま感情で受け取るのではなく、それが本当に正しいものなのかどうか、「なぜ?と屁理屈をこねまくって仮説を立てる」という考え方です。
感情ベースの物事の受け取り方をしているうちは、「自分の主観」から抜け出せていません。
主観というのは自分の物の見方や感じ方であり、その基準はどこまで行っても自分の中だけで完結する視点なんです。
主観に囚われ過ぎている人ほど、自分の常識やルールに凝り固まっていて、無意識に「きっと他の人も自分と同じはず」という期待を相手にしてしまっていることが多いです。そしてその期待に相手が答えなかったとき、主観から外れてしまうので、怒りや悲しみを感じてしまいます。
客観的思考の訓練方法
- 物事をそのまま受け取るのではなく、あらゆる可能性を考え、仮説を立てる
- あらゆる立場になって考えるという
自分の思いついたことだけではなく、その反対意見も考えてみることで客観的思考を訓練できます。
固定観念の解除
固定観念が原因となって、生きづらさから抜け出せなくて、日常の行動が制限されてしまっているのであれば、その固定観念は解除したほうがいいです。
固定観念の解除の方法
- 生きづらさの原因となっている固定観念に気づく
- その固定観念を植え付けた相手が誰かを考える
- 固定観念を疑う
- 固定観念と真逆の事例がないか探す
- その真逆の事実があることを信じる
自分に固定観念を植え付けた人が、「気づいていないフィールド」の人であることもあります。
親が「気づいていないフィールド」の子供は固定観念に縛られる場合、その影響を受けます。
さらに、深掘りしていくと、固定観念を植え付けた人も、固定観念に縛られているのです。
自己肯定感を高める
自己肯定感が低いところから抜け出せない理由
- 自分のことを知らないから
- 世間体や人の評価がベースになった成功体験を積み重ねているから
行動する動機が世間体や人の評価ベースになっているため、いくら成功体験を積み重ねようが、行動する動機が変わらない以上、人の評価ばかりを気にしてしまいます。
せっかく積み重ねた自信も、世間体や人の評価に基づいているため、人の評価がなくなるにつれ、なくなってしまいます。
自己肯定感を高めるために
1.自己満足を日常に散りばめる
思わずテンションが上がる小さな出来事を日常に散りばめることが自己肯定感を高める土台を作る上で必要なことです。
自己満足とは、自分が納得して満足できる物じゃないと、心からの喜びを得ることはできません。
その自己満足を感じたら、その感覚に浸りましょう。
2.普段から自分がいいなと思ったものを選ぶ習慣を身につける
自分がいいなと思ったものは妥協してはいけません。
妥協した選択は、妥協した分の結果と満足感しか得られないはずです。
自分にとって小さないいなを選べない人は、大きないいなを選ぶことはできません。
誰かに直接的に迷惑がかからないようないいなと思えることを選択する習慣を身につけましょう。
やりたいことはやる
成功体験を積み重ねるためには行動する前提になるものを間違えてはいけません。
それは、自分が本当にやりたいことをやるということです。
やりたいことをやるというのは自分の欲望のためなら周囲に迷惑をかけても構わないという訳ではありません。自分の信念を貫くという意味です。
「やりたいこと」「楽しいこと」「ワクワクすること」を構成している要素
- 好奇心
- 能力の上昇
- 主体性意欲
- 他者との結びつき
これらが重なり合っている方が、かなり強い衝動になります。
他者との結びつきとは、人に評価を求めることではなく、人と、「共有したい」「分かち合いたい」ということです。他者の評価が前提でやりたいことを決めてはいけません。
やりたくないことはしない
やりたくないことはしないということは「堕落」「怠惰」ではありません。
仕事したくないから行かない、ダイエットしているのに我慢したくないから食べることとは違います!
やりたいことをやり抜くために、やりたくないことを省くことです。
やりたくないことをしないメリット
- ストレスが大幅に軽減される
- 時間の無駄がなくなる
- やりたいことが明確にわかる
- 「やりたいこと」「やりたくないこと」の自己主張ができるようになる
更なるアイデンティティに磨きをかけるために
アイデンティティとは、自分らしさ、個性のことです。
自分の価値を高めることにより、自分のアイデンティティに更なる磨きをかけることができます。
そしてそれがまた自信になり、好循環が起こります。
人間が生きる意味を見出すための3つの価値
体験価値
何か作品に触れたり、誰かと時間を共有したり、どこかに赴いたりといった自らが体験する価値
態度価値
今の自分が生きている意味を考え、起こった出来事にどんな意味があるのか、これからどうしたいか、その意味を考える価値
創造価値
作品を作り出す価値
作品を作り出すというのは、モノづくりのことです。「やったことない」「モノづくりなんて、できない」という方もいるかもしれませんが、モノづくりの種類も様々です。自分の納得いく作品を作るまでは簡単ではありませんが、趣味でも作品を作っていると、そのできた作品が、作った経験が、自分の強みになります。そしてそれが、自信になります
最後に
本書では、人間のレベル論について、それぞれのフィールドと特性について詳しく書かれています。
ステージアップするにはどうしたらいいか、ステージダウンしないためにはどうしたらいいかなどの、アドバイスも盛り沢山です。
具体例も多く、自分の体験と重なることもあると思います。
レベル論というのは初めて聞いた人には、新しい考え方だと思います。幸せになるためにはこの説を信じてレベルアップするために努力していくことが、心の支えになるかもしれません。
ネガティブな感情になった時に手に取ってもいいし、対人関係に困った時に手に取ってもいい本です。
本を読むだけで、生きる気力が湧いてくるものはなかなかありません。
たまにグサっと言ってくる箇所もありますが、それも作者の優しさだと思います。
本を読んで行動する人が変われる人です。
その一歩を私も応援しています。


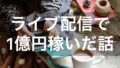

コメント